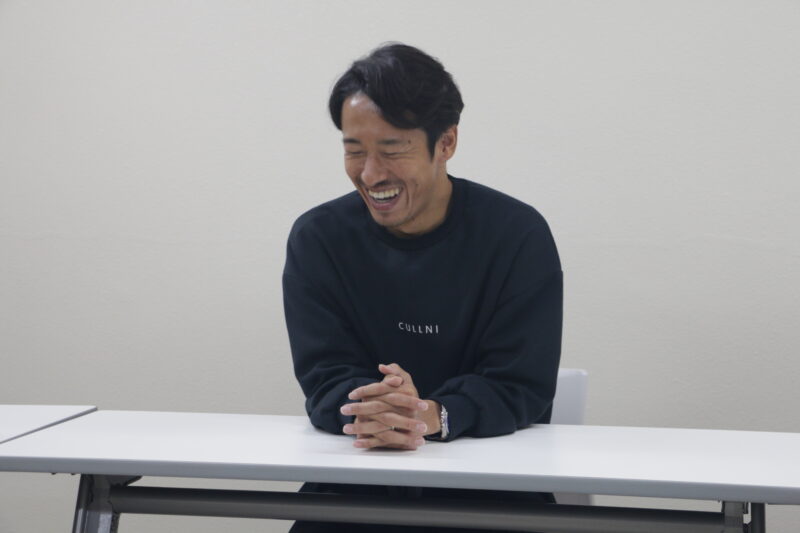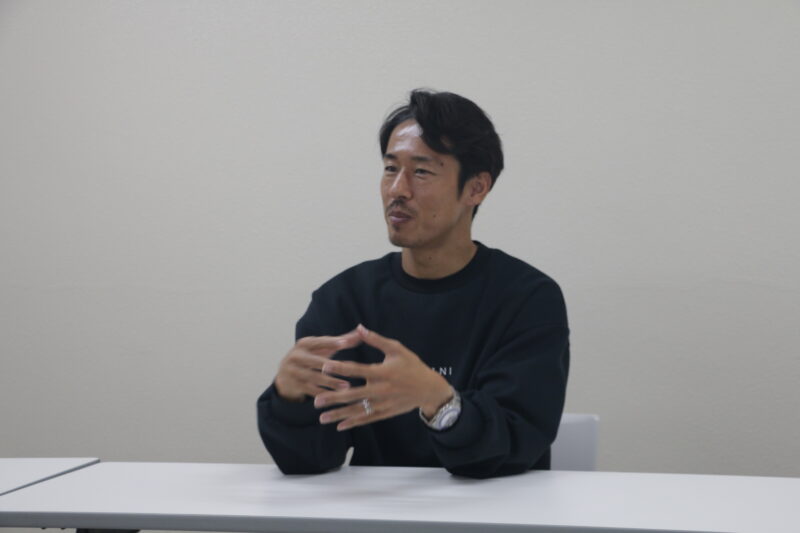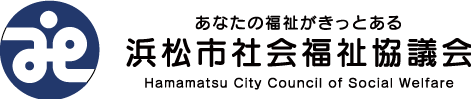【活動レポート】社協だより2025.3月号「NPO法人 ReFrameインタビュー番外編」(浜松地区センター)
はままつし社協だより№197 (令和7年3月号)の「はままつの社会福祉貢献活動」で
NPO法人ReFrame(以下「ReFrame」)副代表の山田 大記さんにインタビューを行いました。
山田さんのReFrameでの活動や皆さんへのメッセージなど、誌面では載せきれなかった熱い思いを番外編として紹介します!
【1】これまでの活動につながる出来事
――社会貢献活動を始めたきっかけを教えてください。――
僕は、ドイツでプレーをしていたことがあるのですが、浜松から離れたことで地域に対する思いが大きくなったことと、ドイツの人たちが、助け合って生活している様子を見たことがきっかけです。
ヨーロッパでは、プロサッカー選手が、地域や社会のために何かをするのは当然のことであり、僕も見習いたいと思っていたんです。ドイツで実現するイメージは湧きませんでしたが、地元で実現したいという思いがありました。
――どのような活動から始めましたか?――
約10年前に個人で児童養護施設へ行き、活動を始めました。小川(ReFrame小川大貴代表)も同時期に小児病棟へ足を運んでいました。
児童養護施設に初めて訪問したのは、クリスマスの日で、子どもたちにクリスマスプレゼントを渡しつつ、一緒にサッカーをしました。子どもたちの喜んだ顔を見て、僕も嬉しくなりました。
――施設で一緒にサッカーをした子の中には、サッカー選手になりたい子もいたでしょうね。――
そうですね。サッカーが上手な子もいます。
3年前のクリスマスの出来事ですが、僕と小川は施設の子どもたちと一緒にサッカーをしていました。その中に、サッカーが上手な男の子がいて「サッカー上手だね。プロのサッカー選手を目指しているの?」と聞いたら「僕はここにいるから、サッカー選手にはなれない」と言っていました。その子自身が、そんなふうに感じていたことも辛かったのですが、施設の職員の皆さんが、周りですごく辛そうな顔をされていたことが、とても印象に残っています。
【2】Reframeの取り組み
—―NPO法人(特定非営利活動法人)を立ち上げたきっかけを教えてください。――
まず、一般社団法人を立ち上げました。僕にとって、その男の子の言葉がすごく大きかったんです。彼の言葉を受けて、自分たちはこれまで何をしてきたんだろう?と感じました。自分たちの活動を振り返って、すごく恥ずかしくなりました。
サッカー選手という立場で、なんとなく表面的に良いことをしていただけで、子どもたちが抱えている本質的な課題には、目を向けようとしていなかったことに気がつきました。「ただの自己満足だったのかもしれない」と一緒に訪問した小川と話しながら帰りました。
その結果、子どもたちが抱えている本質的な課題に、アプローチできるものを考えたいと思いました。表面的なことではなくて、本質的な課題にアプローチできるように活動していこうと、一昨年、一般社団法人を立ち上げました。NPO法人に変更したのは、より多くの方に活動に携わっていただくことを大事にするためです。
――具体的にどんな活動をしていますか?――
子ども食堂の開催やフードパントリー、体験の創出を中心で行っています。
――子ども食堂はどんな場所で行っていますか?――
活動拠点が無く、現在は、月1回くらいの頻度で、様々な場所を借りて実施しています。いずれ常設の多機能型子ども食堂をつくりたいと考えています。
子どもたちの課題は、親御さんが抱える課題にも深く紐づいていて、一つの角度からの支援では解決できないと思います。衣食住に加えて、体験の創出や学習を通して、サポートできるような多機能型の子ども食堂を常設で行うことが目標です。
――子ども食堂では、子どもたちとの食事以外にどのようなことをしていますか?――
ゲームや季節のイベントを用意していて、これらの運営も様々な方に協力いただきながら行っています。例えば、ある銀行の方々から、社会貢献をしたいと思っているけど、何かできないかと相談があったので、考えてきていただいたゲームを子ども食堂で披露してもらいました。
僕たちだけでできることは限られているので、様々な方と協力しながら皆で子ども食堂をつくり、企業や他の団体とのネットワークやつながりを大切にしていきたいと思っています。
――子ども食堂を運営されている方々に伝えたいことはありますか?――
皆さんも熱い思いや強い志を持っていても、何かを成しとげる際に大変さを感じることは、必ずあると思います。その大変さを一人で抱え込むのはすごく苦しいことです。運営者の皆さんには、すでに、たくさんの仲間がいらっしゃると思いますが、やはり仲間をつくることや仲間を頼ることが大切だと思います。
運営に携わってくれた方に対して、迷惑をかけていると感じてしまいがちですが、彼らは「自分も何か手伝いたい!」という思いで、主体的に参加してくれていると思います。必要以上に迷惑はかけられないと考えるのではなく、まずは仲間を信頼して、頼って、一緒に悩みを共有することが大切だと思います。
【3】広がり続ける子どもたちへの支援の輪
――企業や他の団体とのつながりを大切にされているとのことでしたが、その理由を詳しく教えていただけますか?――
理由は二つあります。一つは、僕が誰かと何かを一緒につくるということに、喜びを感じているからです。サッカーは、チームの皆やサポーターと共に、一生懸命戦います。様々な立場の人たちが一緒に戦って、何かを目指すということ、そのプロセス自体が楽しいと感じるんです。
もう一つは、課題を解決するための方法として、協働やネットワークが不可欠ということを多くの方に教えていただきました。僕自身ができることは限られているし、ReFrameという10名のスタッフで構成されるグループでもできることは、限られています。様々な方と一緒に活動させていただく中で、必要なときにお互いに助け合う関係性をつくらなければ、課題を解決していくことは難しいということに気がつきました。
――ネットワークが広がりつつある中で、その成果は感じますか?――
そうですね。ありがたいことにパートナー企業もすごく増えています。すでに思いを持って活動されている方とつながって、お互いの強みを活かすことは、もちろん必要ですし大切なことですが、社会全体で課題解決を進めるためには、課題を知らない方や、課題解決に踏み込んでいない方々に、仲間になってもらうことが重要だと思います。特に、子どもの領域は、人々の存在が重要だと思うんです。精神面のサポートもすごく大切で、人々との関わりでしか解決できません。そう思うからこそ、課題の解決を図る仲間を増やすことは、不可欠だと思っています。
僕も数年前までは、このような課題があることを知りませんでした。現状を知って、いろいろな思いが湧いてきたんです。だからこそ、この課題を知らなかった方に「何かできることをしたい」と言ってもらえること、それは協賛という形だけでなく、いろいろな形で仲間が増えていくということがすごく嬉しいです。それがこの活動を続けていてよかったと思う瞬間です。子どもたちの笑顔を見るのもやりがいの一つですが、仲間が増えたときが特に嬉しい瞬間です。
【4】一人ひとりができる範囲でできる活動を
――ボランティアに関心がないという方たちの中では、「個人がもう少し頑張ってみれば」という声もあります。山田さんがどういう気持ちで活動されているか教えていただけますか?――
活動をしていて感じたことは、自分の努力で、未来を切り開くための環境そのものが、整っていない子どももいるということです。僕は、「サッカーをしたい!」と思った時に始められたこと、努力できる環境が整っていたことがすごくありがたいことだと大人になってから気がつきました。
「助ける」という言葉は少し段差というか、トゲのある言葉なので、 「困った時はお互い様」という気持ちで、地域の皆が寄り添い合い、支え合って課題を解決していくと地域が豊かになっていくのかなと思います。
――山田さんはサッカーとReframeの活動を両立されていますよね。それぞれ仕事や家庭がある中でボランティアとの両立が難しいと感じる人もいると思います。山田さんは、両立という部分において難しさを感じたことはありますか?――
僕は見られ方の不安がありましたね。サッカーだけを、プレーしていてほしいという人も一定数いたので、サッカーに100%注力できていないのではないかと思われてしまうことがありました。僕自身に批判が向くのはいいのですが、ジュビロ磐田を応援してくれている方々が、悲しくならないといいなとは思いました。皆さんからの信頼や期待を裏切ってしまうことになるので、その点は不安でした。ただ、活動を始めてみたら全然そんなことはなくて、「地域のために動いてくれて嬉しい」という声が多かったです。
皆さんにお伝えできることとしては、まずは、自分の家族を大切にすることが一番大切で、何かを犠牲にする必要はないと思っています。仕事をしていたら、ボランティアを始めることは相当難しいことだと思うんですよ。無理のない範囲で、自分にできることをするのも支援の一つなので、大切なことかなと思いますね。
――活動に直接参加することができなくても、間接的に関わる方法もあると思うので、一人ひとりができることに取り組んでくれるといいですね。――
そうですよね。実際に、課題に直面している子どもを見て、顔や情景が思い浮かぶ状態を経験すると、考え方が変わると思います。
強制的にボランティアをするのではなく、衝動的に「やりたいからやる」とならないと絶対に続かないと思うので、その点を皆さんに大切にしてほしいと思います。
――最後にこの記事を読んでいる皆さんへ伝えたいことはありますか?――
いろいろな方から「活動をしてみたい思いはあるけど…」という声をよく聞きます。特に「子ども」って多くの人の思いが、湧きやすい領域だと思っていて、子ども食堂を手伝ってみたいと思ってくださる人は、たくさんいると思うんです。そこで一歩踏み出してもらえたらすごく嬉しいなって思います。
ボランティアは、誰かのためにという思いで行うと思いますが、そのような思いをもっている人たちが集まる空間が子ども食堂や学習支援にはあります。その空間ってすごく温かくて幸せな空間なんです。同じ思いの人たちが集まって、皆で誰かのために、誰かを尊重するという空間が心豊かな空間だと感じます。こんなことをぜひ皆さんにも感じてもらえたらと思います。
【5】新たな取り組み、「浜松こども基金」
――Reframeの活動にボランティアとして参加したい場合、問い合わせてもよいのでしょうか?――
現状は、一般の方の募集は行っていないんです。いずれ募集できるといいなと思っています。
ただ、Reframeを介して一緒に活動していただけるのも嬉しいですが、僕は、仲間という言葉をReframeの仲間という意味だけでなく、子どもたちの課題を解決する仲間という広い意味で捉えています。近くの子ども食堂に手伝いに行ってみようかなと実際に行動していただけたら、直接Reframeに関わることではないですが、すごく嬉しいです。
Reframeを介してというと、現在、「浜松こども基金」という団体の設立に向けて準備しているのですが、その発起人を2025年の1年間募集しているのでご協力いただけたらと思います。「浜松こども基金」というのは、子どもたちへの支援活動を運営されている団体や個人の皆さんは、思いも活動も素晴らしいのに、資金的な部分や人材的な部分で活動が持続していかないという困り事を抱えています。そんな運営者の皆さんを後方支援する団体です。まずは、資金面のサポートをしていきたいと考えています。そして、ゆくゆくは人材などのサポートもしながら地域の活動団体を後押しできればと思っています。「浜松こども基金」を地域の皆さんと共に作れたら嬉しいです。